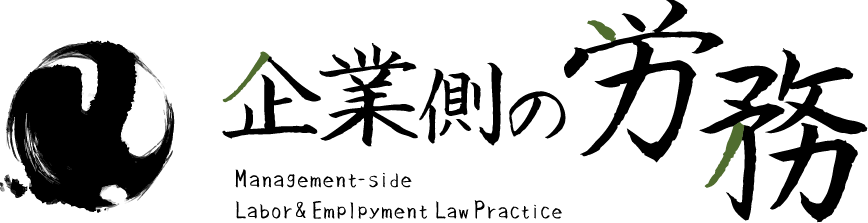「年休権と消滅時効、有休の買取り」
「年休権と消滅時効、有休の買取り」
長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
今回は、「有休を取得する権利(年休権)と消滅時効」について話をし、最後に「有休の買取り」についても触れたいと思います。
1 はじめに
まず、労働者が有休を取得する権利(以下「年休権」と言います)は、一定の要件を満たせば当然に発生します。正確には、「労基法39条に基づく権利は、法定の要件を満たすことにより当然に発生する権利(年休権)と、労働者がこの年休権の目的物(具体的時期)を特定する権利(時季指定権)の2つの権利からなる」と説明されています(白石営林署事件・最二小判昭和48・3・2民集27巻2号191頁)。つまり、一定の要件を満たせば、労働者は(労働者の希望する時期に)有休を取得する権利を取得するのであり、当該権利の発生には使用者の行為は要しないのであり、その後は労働者において、具体的な時期を指定して有休を取得することになるということです。
では、この年休権はどのような場合に消滅するのかを考えてみたいと思います。
2 労働者による有休の取得
まずは、労働者が有休を現実に取得すれば、それによって年休権は消滅します。民法473条は「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅する」と規定しています。
年休権についていえば、債務者は使用者であり、債権者は労働者であるということになります。債務者たる使用者は、債権者たる労働者に対して債務の弁済(有休の取得をさせる)をしたときは、年休権は消滅するわけです。もっとも、年休権に係る債務の弁済は、債権者たる労働者の行為がなければ実現しないものです。したがって、債務者たる使用者においては、債権者たる労働者が有休を取得することを妨害しないことで、債務者としてなすべき義務を果たしていると考えることになります。
3 年休権と消滅時効
⑴ 2年の時効に服する
労基法115条は「…この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定しています。そして、年休権もこの2年間の消滅時効に服すると解釈されています(菅野和夫著「労働法」第12版、㈱弘文堂、2019年P.574)。
すなわち、最初の年休は、雇入れ日から起算して6か月が経過した日に発生しますが、その後2年が経過すれば消滅時効により消滅することになります。
⑵ いつの分から消化されるのか
例えば、労働者Aにつき、令和5年2月時点で、令和3年4月1日に発生した有休が6日残っており、また令和4年4月1日に発生した有休が12日残っている場合、労働者Aが令和5年2月に5日間の有休を取得した場合、この5日間は、令和3年4月1日に発生した有休を取得したものと考えるのか、それとも、令和4年4月1日に発生した有休を取得したものと考えるのかという問題があります。
民法488条第4項第2号が「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。②全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する」と規定していることから、令和4月1日に発生した有休を取得したものとみるべきとの考えもあります。
対して、繰越し分(令和3年4月1日に発生した分)から取得したものと推定するべきとの考えもあります(菅野和夫著「労働法」第12版、㈱弘文堂、2019年P.575、水町勇一郎著「詳解労働法」第2版、(一財)東京大学出版会、2021年P.768、西谷敏著「労働法」第3版、㈱日本評論社、2020年P.378、荒木尚志著「労働法」第4版、㈱有斐閣、2021年P.242)。
繰越し分から取得したというのが、当事者の合理的意思と解釈される場合は多いであろうと思いますが、必ずしもそうではない場合もあるとは思います。実務的には、就業規則等に「労使双方から特段の指定がない場合は繰越し分から取得したものと推定する」とか、「当年分から取得したものと推定する」などという定めを置き、事後に紛争となることを回避しておく必要があります。
4 年休の翌年への繰越しを認めないという考え
もっとも、「年次有給休暇請求権に消滅時効の規定の適用があるというためには、その前提として年次有給休暇請求権のいわゆる繰越しが認められなければならないが、年次有給休暇制度の本来の趣旨からいって、年次有給休暇請求権の繰越しは、これを認めることができないといわざるをえない。」と述べ、年休の翌年への繰越しを認めないとした裁判例があります(静岡地判昭和48・3・23/判例タイムズ291号177頁)。この裁判例を理論的に妥当と評価する学者もいますが、一般的な考え方とは言えません。
5 有休の買取り
これについて、菅野和夫著「労働法」第12版、㈱弘文堂、2019年P.575は「買取りを予約し予約された日数につき有休取得を認めないことは労基法39条違反であるが、結果的に未消化の有休日数に応じて手当を支給することは違法ではない」旨を述べています。荒木尚志著「労働法」第4版、㈱有斐閣、2021年P.242も「年休の買上げを予約し、買上げ対象とされた日数の年休取得を認めないことは労基法39条違反となり許されない。ただし、労働者が退職する場合における未消化年休の買上げについては、ILO 132号条約や諸外国でも年休手当の精算を認めているところであり、労基法上も認めるべきであろう」と述べています。
もっとも、「年休が時効や退職等によって消滅した場合に、その日数に応じて金銭を支払ういわゆる『事後の買上げ』については、年休の取得を制約するわけではないので労基法39条に違反しないとする見解が一般的であるが、このような取扱いが容認されると、事後的に金銭の支払いを受けることを期待して労働者が現実の年休取得を控える行動に出ることが考えられ、年休制度の趣旨に反する事態を招きかねない。したがって、事前・事後を問わず、未消化年休に対して使用者が金銭を支払うことは、原則として労基法39条に違反し無効と解すべきである。ただし、解雇、退職勧奨など使用者の意向により退職に至ったために労働者が年休を消化できなかった場合、および、計画年休で予め設定されていた年休を年休日前に退職したため取得できなかった場合については、これらの効果をもたないと考えられるため、労基法に違反するものではないと解されよう」という見解もあります(水町勇一郎著「詳解労働法」第2版、(一財)東京大学出版会、2021年P.769)。
弁護士 植木 博路
(長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っています)